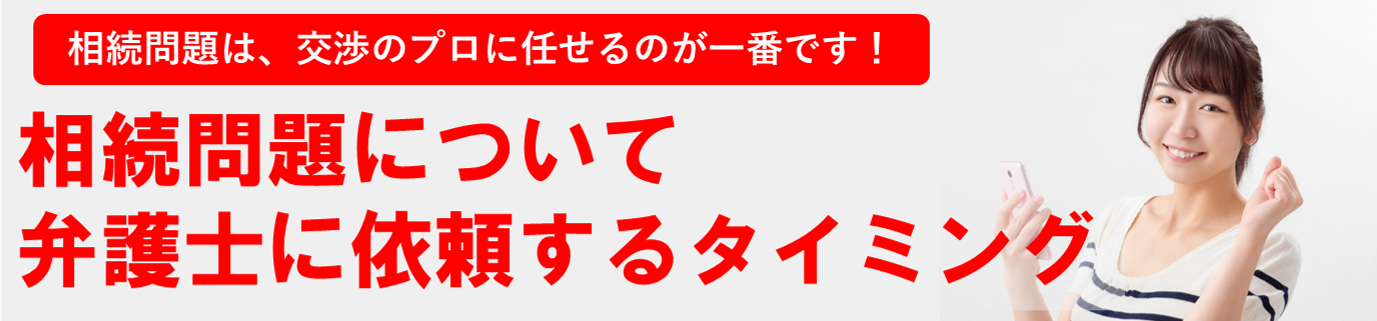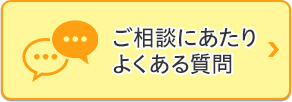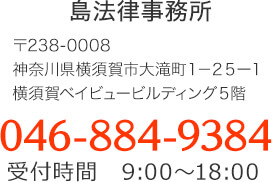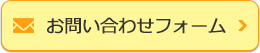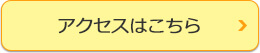Q&A 相続財産が自宅不動産しかなく、同居している子供に相続させたいと考えている場合
〇この記事を読むのに必要な時間は約3分です。
質問
相続財産が自宅不動産しかありません。また同居している子供に自宅を相続させたいと考えています。
何か良い方法はあるでしょうか?
解答
相続では、原則として、相続財産について、各相続人が法定相続分に応じて共有することとなります。
その相続分を、被相続人の意思で変更するには遺言が必要となります。
今回のケースでは相続人がお子様一人の場合には、お子様がすべてを相続することになるため、お子様に自宅不動産を引き継ぐことができますが、他に相続人がいる場合には、お子様に自宅不動産を残したい場合には遺言を作成する必要があります。
また、遺言を残す際には、他の相続人の「遺留分」に配慮することも必要です。
「遺留分」とは、被相続人による財産処分の自由と相続人の生活の安定・財産の公平な分配の調整という見地から定められた制度で、被相続人の配偶者、子(代襲者を含む)、直系尊属は、被相続人の財産のうち、一定の割合が「遺留分」として保障されています(民1028条)。
したがって、唯一の相続財産である自宅不動産をすべてお子様に遺贈等する場合、お子様は他の相続人から遺留分減殺請求権を行使される可能性があります。
具体的には、本来の法定相続分で認められた法定相続分の半分が遺留分として各相続人に認められています。
減殺請求権が行使された場合、遺留分減殺請求の相手方は、現物を返還することが原則ですが、価格弁償することも可能です(民1041条)
したがって、お子様に遺留分相当の財産を弁償する資力があればお子様が単独で自宅不動産を引き継ぐことが可能です。
しかし、お子様に弁済の資力が無い場合には、自宅不動産はお子様とその他相続人との共有となってしまします。
ただ、遺留分減殺請求の行使は、各相続人の意思に委ねられているため、その他相続人が遺留分減殺請求権を行使しない場合には遺言の通りの相続が可能となります。
上記のような事態を未然に防止するためには、家庭裁判所の許可を得て、生前にその他相続人に遺留分を放棄させる(民法1043条1項)方法もありますが、大抵生前に誰か一人の相続人に有利な遺言を残そうとするだけで火種を残すこととなりますので、このような放棄をさせることは難しいのが通常です。
なお、保険金の受取人が指定された生命保険金(死亡保険金)は、固有財産となり、相続財産の対象とはなりませんので、お子様に遺留分相当額を支払う資力がない場合には、お子様を受取人とした生命保険に加入しておくことも良いかと思います。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2023.10.24解決事例葬儀・墓などの費用全額を遺産から支出してもらい残額を法定相続分で分割して解決した事案
- 2023.10.24解決事例調停にて使途不明金を追求して流動資産のすべてである数千万円を獲得して解決した事案
- 2023.05.31解決事例先妻の子に相続放棄してもらい解決した事案
- 2023.04.24解決事例話し合いのできない相手方と複数の相続案件を調停にて代償金で解決した事案
- Q 遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。
- Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
- Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。
- 相続財産である不動産について、法定相続人の一人が法定相続分にしたがった相続人3人の共有名義で相続登記をしてしまいました。他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。
- Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。
- 生命保険金は相続財産に含まれますか?
- 相続におけるクレジットカードの取り扱いについて気を付けることはありますか?
- Q&A ハンコ代について教えてください。相場はありますか?
- 賃料収入がある不動産について相続まで待つのと生前贈与のどちらがメリットが大きいといえるでしょうか?
- Q&A 「死んだらあげるから」という口約束は有効?【弁護士が解説】