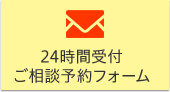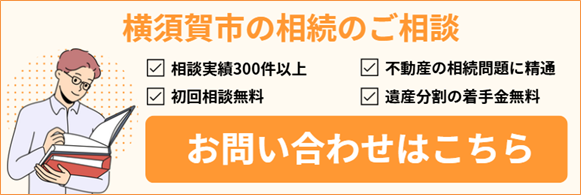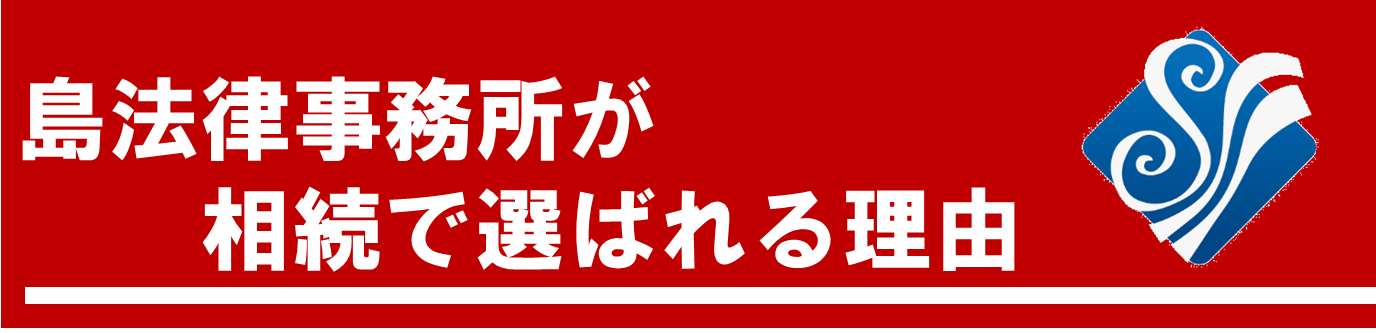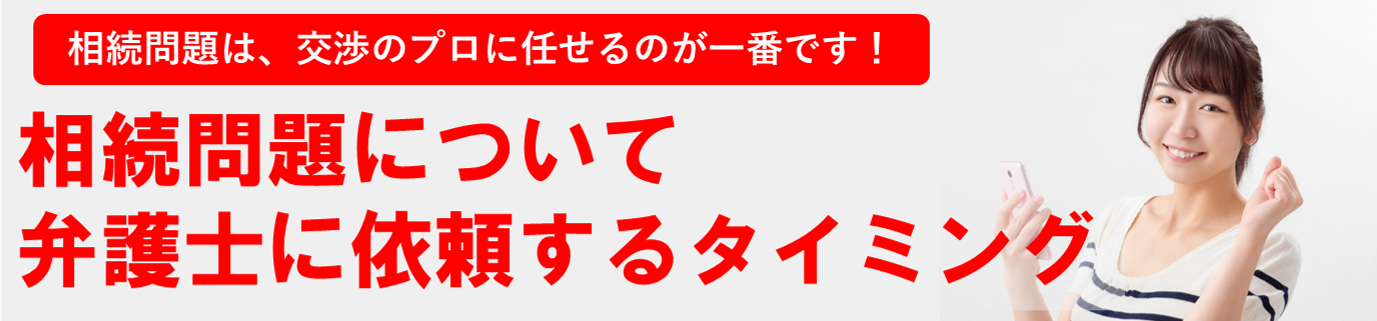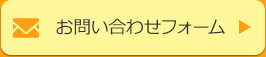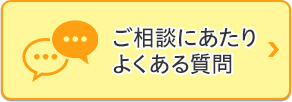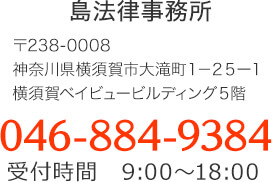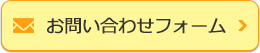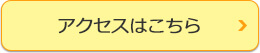相続人なのに遺産や遺留分をもらえないことがあるのか
目次
法定相続人であるにもかかわらず、遺産をもらえないケースがあります。遺産がもらえなくても、遺留分をもらえるのが通常です。
しかし、中にはこの遺留分すらもらえないケースもあります。
以下説明していきます。
1 法定相続人なのに遺産をもらえない場合
ここでは、法定相続人なのに遺産がもらえないケースについて解説します。
遺言があるとき
遺産の全部を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺言者が死亡して相続が開始すれば、遺産分割を経ないで当然に全遺産が特定の相続人に移転することになります。
遺産の全部を相続する相続人以外に遺留分を有する法定相続人がいる場合は、この遺言により遺留分を侵害されることがあります。
相続人以外に遺贈する旨の遺言があるとき
遺言者の全財産を相続人以外の人に遺贈する旨の遺言がある場合も、法定相続人が遺産を受け取れなくなることがあります。
遺留分を有する法定相続人がいる場合は、この遺言により遺留分を侵害されることがあります。
相続廃除されたとき
家庭裁判所による推定相続人廃除の審判がなされた場合、当該推定相続人は相続人となれないため、遺産をもらえなくなります。
・推定相続人が被相続人に対して虐待をした
・推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えた
・推定相続人にその他の著しい非行があった
廃除の審判が確定したとき又は調停が成立したときは、被相続人の死亡時にさかのぼって廃除の効力が生じます。
相続人が民法所定の相続欠格事由に該当するとき
民法所定の相続欠格事由に該当する者は、相続人になれません。
・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
以上の場合が該当します。
2 相続人なのに遺産をもらえない場合の対処法
相続人なのに遺産をもらえない場合の対処方法を説明します。
遺言書の無効を主張する
以下のような事情がある場合には、調停又は裁判を起こして遺言の無効を主張できます。
・形式的要件を満たしていない(自筆証書遺言の場合)
・遺言書作成当時、遺言者に遺言能力(意思能力)がなかったことが疑われる
・本人の筆跡に似せて第三者が遺言書を偽造・変造した可能性がある
・第三者による脅迫・詐欺により遺言が作成された可能性がある
他の相続人に遺言と異なる遺産分割協議を申し入れる
有効な遺言がある場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割を行えます。
遺言の内容に納得できない場合は、他の相続人や包括受遺者に対し、遺産分割協議を申し入れるのも一つの方法です。
ただし、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の合意も得なければなりません。
遺留分侵害額請求を行う
遺言により、自己の遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求権を行使することにより、法律で最低限保障された遺産の取り分をもらえる可能性があります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた権利です。
特別受益の持ち戻しを求める
相続人の中に多額の生前贈与等を受けた人がいる場合には、まずは遺言によって持ち戻し免除の意思が表示されていないかを確認します。
持ち戻し免除の意思表示がない場合は、遺産分割協議において特別受益を相続財産に持ち戻すよう主張します。
持ち戻しとは、特別受益を相続分の前渡しと考えて、計算上相続財産に加算し、これを相続財産とみなすことです。
不当利得返還請求を行う
相続人の1人が遺産を独り占めして使い込んでいることが疑われる場合は、まずは使い込みの証拠を収集しましょう。預貯金の使い込みが疑われる場合は、被相続人名義の口座の取引履歴を金融機関から取り寄せて入出金履歴を確認します。
使い込みの事実が確認できた場合、遺産を使い込んだ相続人に対して、法定相続分を限度に不当利得返還請求を行えます。
3 相続人なのに遺留分をもらえない場合
相続権を有していても遺留分をもらえない相続人は以下の通りです。
被相続人の兄弟姉妹
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
被相続人の甥姪
被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められない以上、その代襲相続人である甥・姪にも遺留分は認められません。
4 遺留分が認められない相続人が遺産を取得するには
下記の方法があります。
遺言の無効を主張する
遺言があっても、形式的要件を満たしていない場合や、遺言書作成当時、遺言者に遺言能力がなかったことが疑われる場合などには、遺言の無効を主張できる可能性があります。
寄与分を主張する
被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人が、被相続人の生活の世話や病気の看護をしたり、無償で家業を手伝ったりして、被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合は、寄与分を主張できる可能性があります。
以上、相続人なのに遺産をもらえない場合について説明してきました。
どのような手段を講じるかは、ご自身だけで判断せずに、専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続事件に注力する弁護士だから出来るアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2026.01.18婚外子がいた場合遺産分割はどうなる?分割割合を相続に強い弁護士が解説
- 2026.01.18遺贈寄付をお考えの方へ 手続きからメリットまで弁護士が解説
- 2025.12.21相続の遺産分割とは?揉めやすい不動産の評価額算出と分割方法を弁護士が解説
- 2025.12.21売却価格 vs 評価額のズレが争点!不動産の遺産分割で時価を主張すべきケースとは