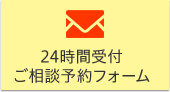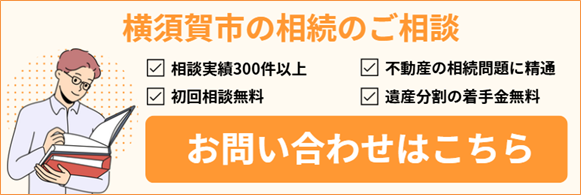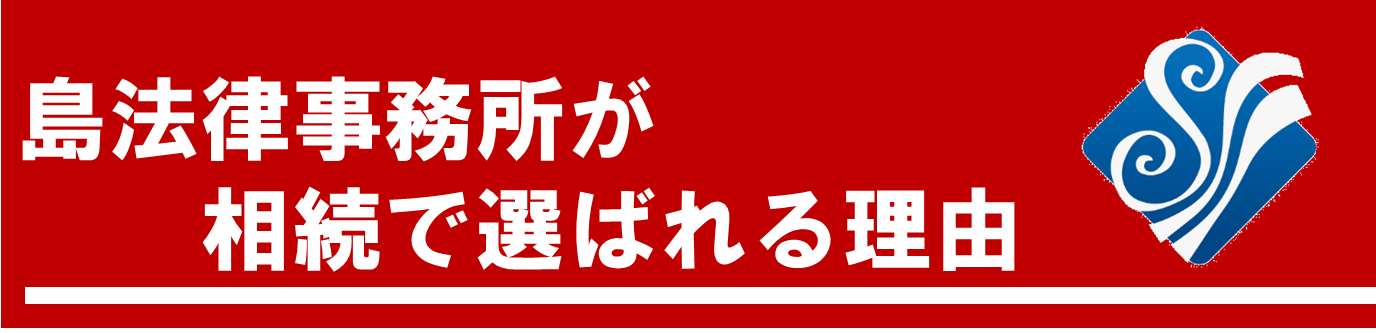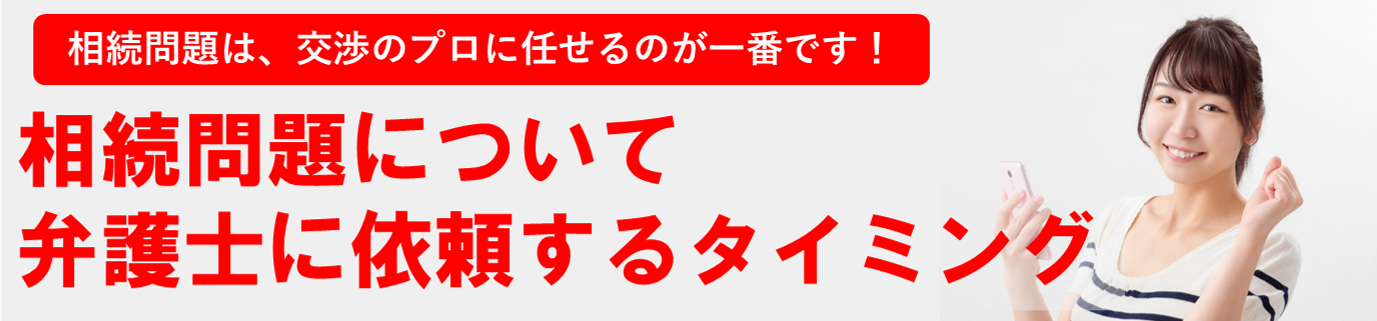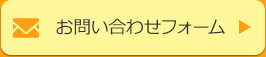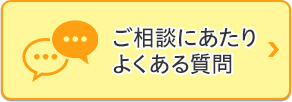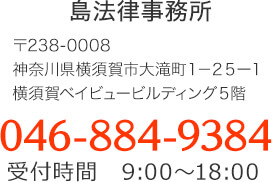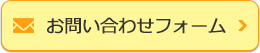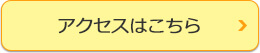相続人以外にも寄与分は認められるのか
目次
相続人以外であっても介護などで貢献してきた場合、寄与分は認めらるでしょうか。
以前は認められませんでしたが、民法改正により特別寄与料が認められる可能性があります。
従来の「寄与分」制度
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした人がいる場合に、その貢献度に応じて、その相続人の相続分を増やす制度です。
現行の民法では、寄与分が認められるのは相続人に限定されており、相続人以外の方には認められません。
新設された「特別寄与料」制度
特別寄与料とは、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供を行い、これにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与があったと認められる場合に、当該親族が相続人に対してその寄与に応じた相当額の金銭の支払いを請求できる権利を指します。
特別寄与料を請求できるのは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族が該当します(民法725条)。
内縁の配偶者や事実婚のパートナー、離婚した元配偶者などは民法上の親族に該当しないため、特別寄与料を請求することはできません。
特別寄与料が認められるための4つの要件
1.相続人以外の親族であること
2.「特別の寄与」をしたこと
請求者は、被相続人に対して療養看護その他の労務の提供を行ったことが必要です。寄与分と異なり、財産給付が含まれていないため、被相続人の事業に出資をしたとしても特別寄与料の対象にはなりません。
3.相続財産が維持・増加したこと
提供された特別な労務によって、被相続人の財産が維持または増加したという因果関係が必要です。
4.労務の提供が無償でなされたこと
療養看護その他の労務の提供が無償で行われたことが必要です。もし、労務の対価として相当な報酬を得ていた場合、改めて特別寄与料を請求することは二重の利益取得にあたるため認められません。
特別寄与料の請求方法と期限
まず、相続人に対し請求しましょう。
当事者間の話し合いで解決できない場合、特別寄与者は家庭裁判所に特別の寄与に関する処分調停を申立てることができます。
調停での話し合いがまとまらない場合、調停は不成立となり、自動的に特別の寄与に関する審判の手続きに移行します。
審判では、家庭裁判所が、当事者から聴取した事情や提出された証拠などを総合的に考慮し、特別寄与料の請求を認めるかどうか、また認める場合の金額などを最終的に判断します。
請求期限には注意が必要です。特別寄与者が、相続の開始および相続人を知ったときから6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、特別寄与料の支払いを求めることができなくなります。
新しい制度だからこそ、弁護士にご相談ください
以上、特別寄与料について説明してきました。
実際には、まだ数年しか経っていない制度のため、ご自身が該当するかどうかを簡単には判断できないかと思います。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
当事務所の初回無料相談をご利用ください
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続案件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2026.01.18婚外子がいた場合遺産分割はどうなる?分割割合を相続に強い弁護士が解説
- 2026.01.18遺贈寄付をお考えの方へ 手続きからメリットまで弁護士が解説
- 2025.12.21相続の遺産分割とは?揉めやすい不動産の評価額算出と分割方法を弁護士が解説
- 2025.12.21売却価格 vs 評価額のズレが争点!不動産の遺産分割で時価を主張すべきケースとは