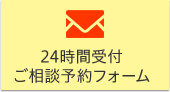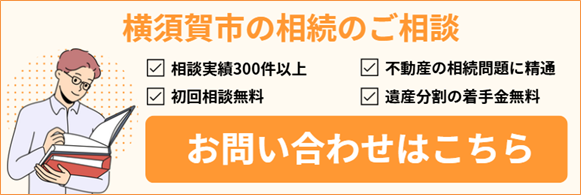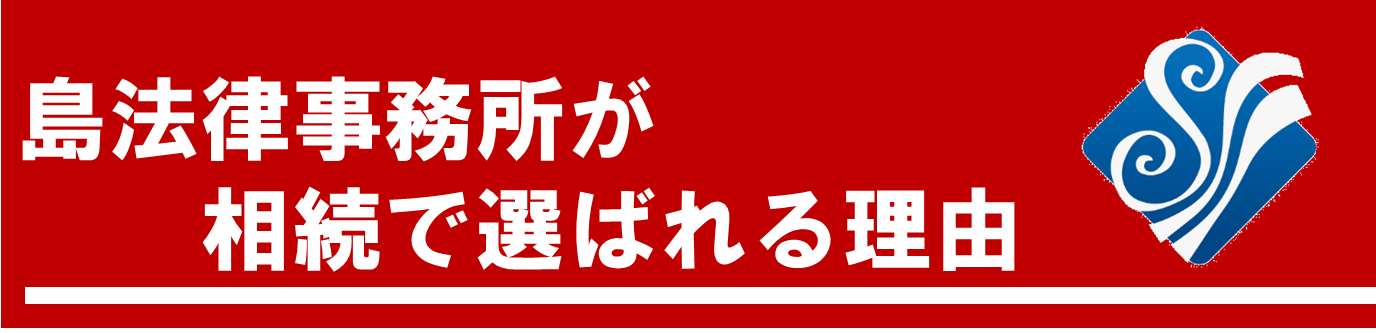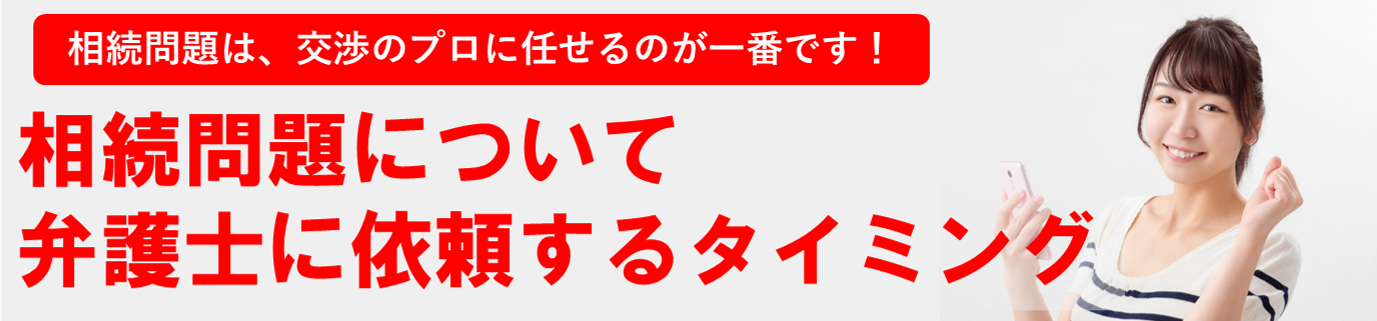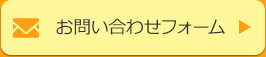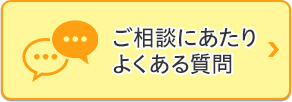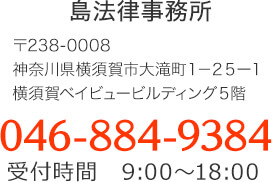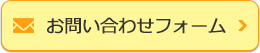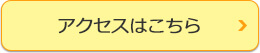相続人が行方不明で遺産分割ができないときの対処法
目次
相続人の中に連絡が取れない人や、長年行方不明になっている親族がいる場合、遺産分割をしたくてもできない状態になります。
そんなときに活用できるのが、「不在者財産管理人」の選任制度です。
家庭裁判所の手続きを通じて、不在者に代わる管理人を選任し、その人が代理人として遺産分割に参加することで、法的に有効な遺産分割協議が可能になります。
以下で説明していきます。
不在者財産管理人制度とは
不在者財産管理人とは、行方が分からない相続人に代わって、その財産を管理する者として家庭裁判所が選任する管理人のことをいいます。
この制度を活用することで、不動産の売却や相続税の手続などを進めることができます。
制度の対象となる「不在者」の定義
不在者とは、従来の住所や居所を去り、容易に帰ってくる見込みがない者を指します。
- 以前の住所・居所を去っていること
- 戻ってくる見込みがないこと
- 現実にその者に連絡が取れず、居所も不明であること
が必要です。
制度を利用できるケース
不在者財産管理人制度は、財産を保全する必要がある場合にのみ適用されます。
反対に、不在者が財産を何も持っていない場合や、すでに他の管理人がいる場合には、制度の利用は認められません。
次のような場合に利用されます。
- 相続人の1人が長期間連絡が取れない
- 被相続人の不動産を売却・処分したいが不在の相続人の許可だけが取れない
他の制度との比較
不在者の相続対応においては、不在者財産管理人制度のほかにも失踪宣告制度や認定死亡制度が選択肢となり得ます。
① 失踪宣告制度(民法30条〜31条)
失踪宣告制度は、不在者の死亡を法律上擬制する制度であり、戸籍上も「死亡」と記載されることになります。
この宣告が確定すると、相続は開始し、不在者の相続人がその財産を承継することになります。
② 認定死亡制度(戸籍法89条)
認定死亡制度は、水難、火災、その他の事故・災害などによって死亡が確実視されるが遺体が見つからない場合に、関係官庁からの報告をもとに死亡として戸籍に記載する制度です。
これは、あくまで行政実務上の取り扱いであり、法律上の死亡の擬制とは異なります。
③ どの制度を選択すべきか
不在期間が比較的短く、帰来の可能性も否定できないときは不在者財産管理人の選任がよいでしょう。
不在から長期間(7年以上)経過し、生死も不明で連絡手段も尽きているときは失踪宣告を検討しましょう。
災害や事故等により死亡がほぼ確実だが遺体が確認できないときは認定死亡制度又は特別失踪宣告を利用することになります。
まとめ:専門家である弁護士に相談を
以上、相続人が行方不明で遺産分割が出来ない時の対処法を説明してきました。
実際には事案ごとになすべきことが異なり、一般の方が判断するには難しいといえます。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続を専門として多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2026.01.18婚外子がいた場合遺産分割はどうなる?分割割合を相続に強い弁護士が解説
- 2026.01.18遺贈寄付をお考えの方へ 手続きからメリットまで弁護士が解説
- 2025.12.21相続の遺産分割とは?揉めやすい不動産の評価額算出と分割方法を弁護士が解説
- 2025.12.21売却価格 vs 評価額のズレが争点!不動産の遺産分割で時価を主張すべきケースとは