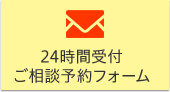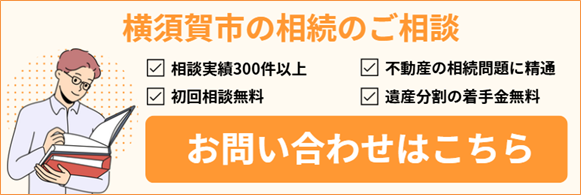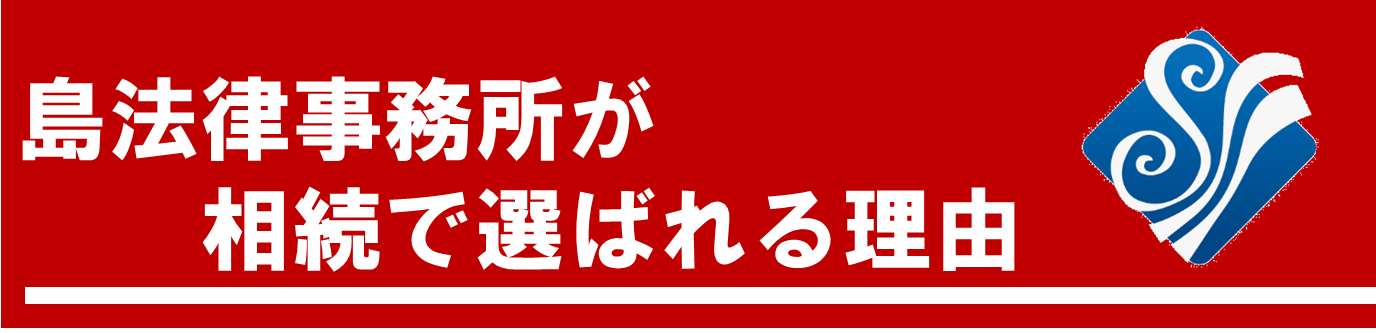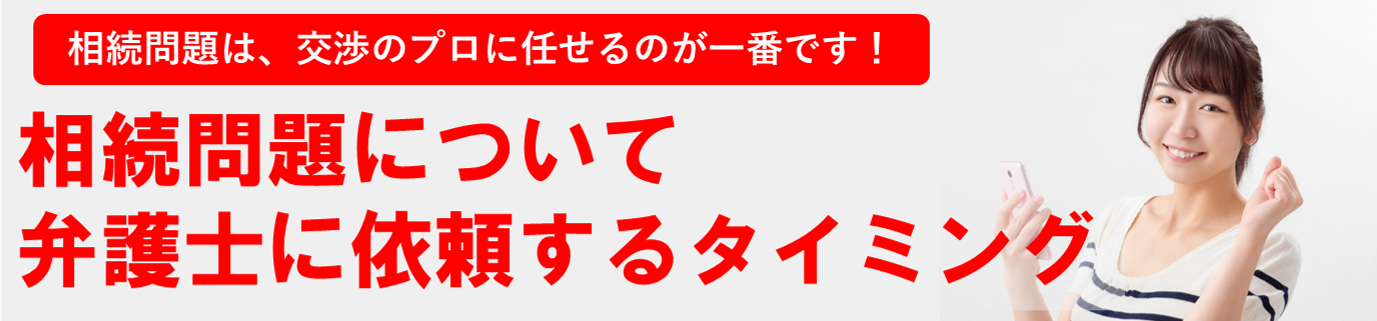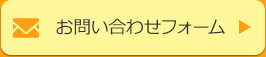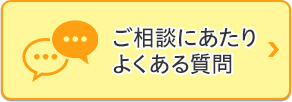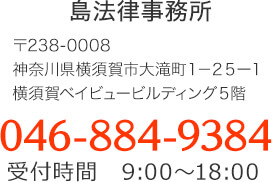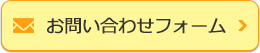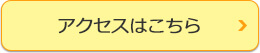相続した不動産の管理について
目次
相続した不動産をどう管理するかについて問題になることがあります。
以下説明していきます。
遺産分割までは共有となる
相続した不動産をどう管理するかについて問題になることがあります。
以下説明していきます。
不動産は遺産分割が終わっていない段階では、相続人全員が共有することになります。
共有の場合、不動産の処分や借地借家法の適用される賃貸契約をするには、原則として相続人全員の同意が必要になります(民法251条、252条など)。
相続人のうち1人が、他の相続人の同意を得ずに共有不動産を第三者に売却したり、長期の賃貸借契約を結んだ場合、その行為は他の相続人の共有持分権の範囲では無効になる可能性があります。
民法252条1項により、不動産の修繕や維持管理、短期の賃貸借契約などの「管理行為」については、全員の同意は不要であり、持分価格の過半数で決定することができます。
これに対し、雨漏りの修繕、草刈りなどの修繕行為は各共有者が単独で行うことができます。
相続人の中に所在不明者がいる場合
相続財産に不動産が含まれている場合に相続人の中に連絡のつかない者がいる場合、その相続人の同意を得ることができず、不動産の処分ができません。
こうした状況に対応するため、令和3年の民法改正によって新たに導入されたのが民法262条の3「所在等不明共有者の持分の譲渡に関する裁判」という制度です。
この制度では、以下のような要件を満たせば、裁判所の判断を経て「所在等不明共有者の持分も含めて」不動産全体を売却できるようになります。
- 他の共有者の所在が不明であり、合理的に調査しても見つからないこと
- 申立人以外の全ての共有者が、特定の第三者に持分を譲渡することに合意していること
- 譲渡対象が不動産全体であること
この手続をとることで、所在不明者の持分を譲渡する権限が裁判所から与えられ、他の共有者と一緒に不動産全体を売却することが可能となります。
なお、譲渡価格に相当する金額は供託し、後日所在不明者が現れた場合の権利を保全する形が取られます。
遺産共有の場合は相続開始から10年の経過が必要
遺産共有の場合は相続開始から10年経過も要件になります。
民法262条の3第2項により、相続開始から10年が経過していないと、譲渡権限を得るための裁判を起こすことができません。
たとえ他の相続人が売却を望んでいても、相続開始から10年が経過するまでは、この制度によって不動産全体を処分することはできないのです。
所在不明者の存在が不動産の売却や活用を阻んでいる場合、以下の選択肢があります。
- 不在者財産管理人の選任(家庭裁判所で申立て)
- 共有物分割訴訟の提起(共有関係の解消を目的とする)
- 民法262条の3による裁判手続の活用(所在等不明共有者の持分を譲渡)
どの方法を選ぶべきかは、ケースによって変わってくるため、弁護士に相談することをお勧めします。
共有状態を解消するための方法
① 不在者財産管理人を選任すべき場合
相続人の中に「生きてはいるが連絡が取れない」「居所が不明である」といった者がいる場合には、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任するという方法もあります(民法25条以下)。
不在者財産管理人は、所在不明者に代わってその財産を管理・処分する法的権限を与えられた者であり、以下のような手続が可能になります。
- 遺産分割協議への参加・同意
- 不動産売却への承認申請
- 管理費・税金の支払い代行
ただし、管理人は「不在者本人の利益を守る」立場であり、自由に売却や処分ができるわけではありません。
所在等不明者がいるが相続開始から10年が経過していないというケースでは、有力な手段として検討されます。
② 共有物分割請求(民法258条)
共有状態が続き、協議での解決が困難な場合には、家庭裁判所に共有物分割訴訟を提起することができます。
裁判所は、「現物分割」「代償分割」「換価分割」のいずれかの方法で判決を下し、共有関係を強制的に解消することが可能です。
相続不動産トラブルを事前に防ぐ方法
相続トラブルを避けるうえで最も有効なのが、被相続人の生前対策です。
- 遺言書の活用 自筆証書遺言や公正証書遺言により相続人間の争いを大幅に抑制できます。
- 家族信託(民事信託)の活用 高齢になった親が認知症になる前に、不動産の管理・処分権限を子に託すことができます。信託契約によって、誰が管理し、誰に利益を分配するのかを柔軟に設計できる点が大きな特徴です。
相続開始後は早期の遺産分割が大切
相続が発生した後、遺産分割協議をせずに不動産を放置すると、以下の問題が生じます。
- 共有者の1人が死亡し、さらに相続人が増える
- 利用状況や費用負担に差が生じ、不満が蓄積する
そのため、相続開始後なるべく早い段階で遺産分割協議をすることが大切です。
専門家への相談が解決の近道
以上、相続した不動産の管理について説明してきました。
煩雑な手続きが必要であり、法的な知識なしに遺産分割したり、放置することは後悔することになりかねません。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続案件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2026.01.18婚外子がいた場合遺産分割はどうなる?分割割合を相続に強い弁護士が解説
- 2026.01.18遺贈寄付をお考えの方へ 手続きからメリットまで弁護士が解説
- 2025.12.21相続の遺産分割とは?揉めやすい不動産の評価額算出と分割方法を弁護士が解説
- 2025.12.21売却価格 vs 評価額のズレが争点!不動産の遺産分割で時価を主張すべきケースとは